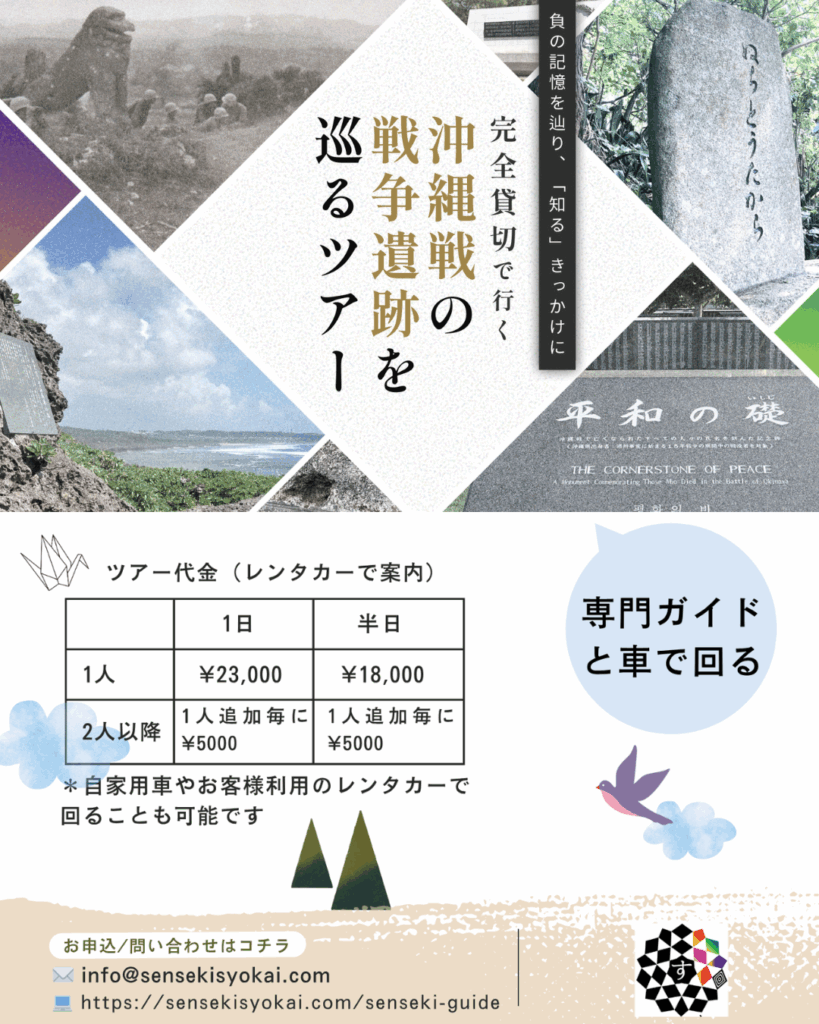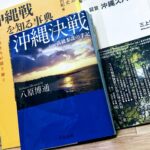糸満市米須周辺は沖縄戦の最終盤にかけて激戦になった場所です。
日本の第32軍の司令部が首里から米須近くの摩文仁に撤退したことから、アメリカ軍との間で住民を巻き込んだ激しい戦闘が起きました。
✔️あわせて読みたい
日本兵、アメリカ兵はもとより避難してきた住民、もともといた住民も巻き込み「鉄の暴風」と言われた砲撃にさらされ多くの住民の命が失われました。
首里が陥落し、主戦場が本島南部にうつった5月31日以降、6月23日の沖縄戦終結までの1ヶ月で実に沖縄戦での全住民の犠牲者の半数以上が亡くなっています。
米須周辺でも多くの方が亡くなりました。
戦後すぐ、周辺に散乱していた遺骨3万5000柱の遺骨を納めたのが、今回紹介する「魂魄の塔」です。
地元の人の尽力により沖縄で戦後最も早く建てられた「魂魄之塔」
沖縄戦終結とともに沖縄県民はアメリカ軍の民間収容所に入ります。収容所では飢えや病気で亡くなる方も多く、戦争を生き抜いても苦難が続きます。
その後数ヶ月で収容所を出て、地元に戻る方もいましたが、地元に戻ることも許されず他の場所に移住することを命じられた住民も少なからずいました。
命じたのはアメリカ軍で、従来住民が住んでいた土地を基地やなんらかの形で利用すること、移住により食料の生産を増やすことが主な理由でした。
1946年1月真和志村(現在の那覇市)の住民も戦後、帰村を認められず糸満市米須に移住を命じられます。
米須は激戦地で住民も多く亡くなった場所であり、一帯は戦没者の遺骨が「道路、畑の中、周辺いたる所に散乱していた」状態(碑文に記載)でした。
実際に米須での遺骨収集に携わった翁長安子さんから、筆者が直接聞いた証言も紹介します。
遺体を肥料にして植物が育ち、大きな作物を引き上げると、大きな頭と小さな頭二つの骨が見つかった。髪の毛から母親と子ども2人とわかった。
翁長安子さんの証言より一部抜粋
真和志村の「金城和信村長」が、(遺骨収集することに難色を示していた)アメリカ軍と交渉をし、許可を得て遺骨収集を始めました。
戦前は沖縄の小学校の校長などを歴任。
戦後は真和志村の村長となり遺骨収集を積極的に行い「魂魄之塔」や建立に尽力。
尚、金城和信さんの娘二人が「ひめゆり学徒隊」として伊原第三外科壕で戦死したため、伊原第三外科壕の上に「ひめゆりの塔」を建立。その他カ「健児の塔」も建立。

遺骨を石で囲み、1946年2月「金城和信村長」が「魂魄之塔」を建立しました。
読み方は「こんぱくのとう」です。
※「魂魄之塔」と命名したのは翁長助静(糸満高校真和志分校の校長。後の村長。前沖縄県知事翁長氏の父親)
周囲に慰霊碑が立ち並ぶ現在の「魂魄之塔」

周囲には平和学習で訪れた学生さんが手向けた折り鶴があった。
那覇方面から国道331号線で「ひめゆりの塔」を超えるとすぐに、右側に「ひむかいの塔」が見えてきます。「ひむかいの塔」の交差点を右に曲がって5分ほど畑の中を走ると、「魂魄之塔」に到着します。

「魂魄の塔」の前に駐車スペースがあるので、車で訪れることが可能です。「魂魄の塔」周辺は、各県の慰霊碑も立ち並び、静かで厳かな雰囲気です。
周囲の慰霊碑で一際目立つ、まんじゅうのような「こんもり」とした慰霊碑が「魂魄の塔」です。碑文によると、3万5000柱が集められ大規模な慰霊碑となりました。

1957年琉球政府は戦没者の遺骨を一括管理する方針のもと、那覇市識名に「戦没者中央納骨所」を建設し各地の遺骨を集約させました。
この流れは以下で紹介した「栄里の塔」も同じです。
✔️あわせて読みたい
「魂魄之塔」も1975年遺骨を「戦没者中央納骨堂」へ移動しました。
※現在糸満市摩文仁の「国立沖縄戦没者墓苑」に集約されています。
「魂魄之塔」は兵士だけではなく、多くの住民が亡くなった沖縄戦で戦後「遺骨がどのような状態だったのか」、「遺骨がどのように収集されたのか」などがわかる貴重な慰霊碑です。
尚、「魂魄之塔」の敷地内には「金城和信村長」の像があります。近くには「金城和信村長」も関わった「ひめゆりの塔」もありますので、一緒に回るのがおすすめです。
【魂魄之塔】
- 住所
- 232 278 759*61 マップコード
- 駐車場
- 比較的大きな駐車場あり