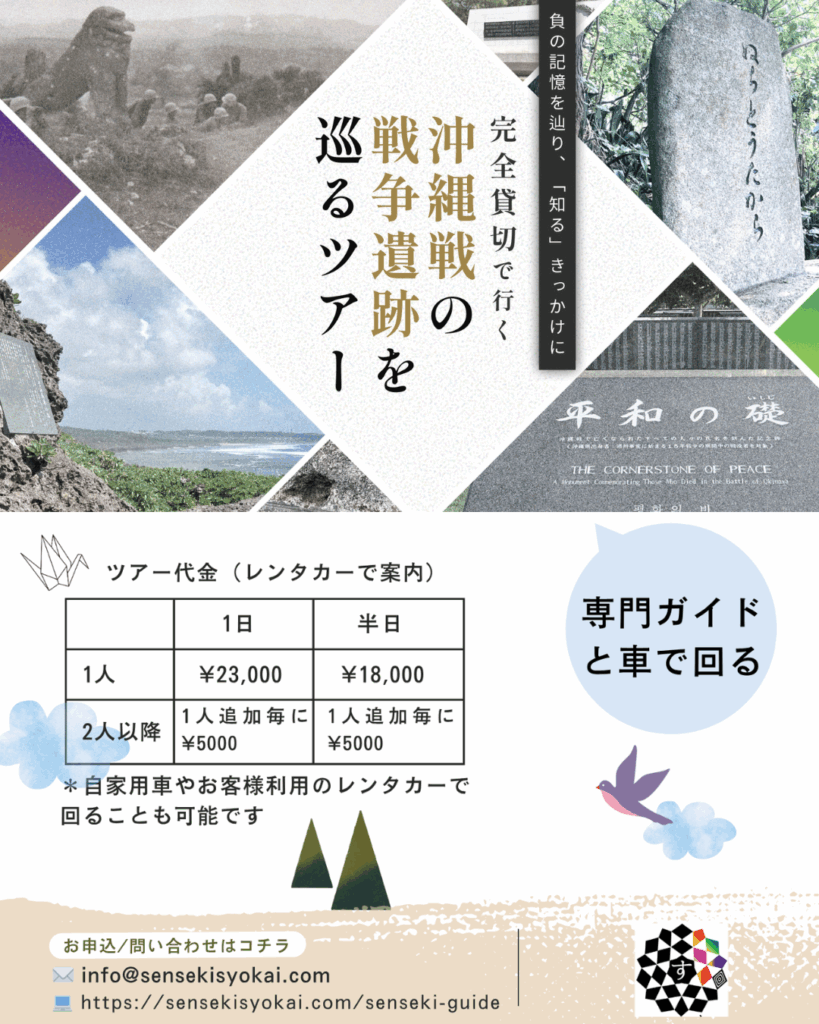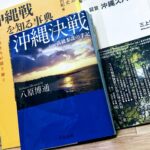「人生の蕾のまま戦場に散った学徒兵」
この文は故「大田昌秀」沖縄県元知事の著『沖縄鉄血勤皇隊』の副題です。
人生花開く前に、戦争により命を奪われた10代の学生達。戦争がなければ青春を謳歌し、輝かしい将来が待っていたことでしょう。
沖縄戦では12の男子の学校の生徒、先生が法的根拠もないまま動員されました。
✔️あわせて読みたい 12の男子の学校の一つ「一中生徒」の沖縄戦
そのうちの一つ。冒頭紹介した「大田昌秀」沖縄県元知事も配属された学徒隊「師範鉄血勤皇隊」とその犠牲者を祀る「沖縄師範健児之塔」を紹介します。
「沖縄師範学校男子部」は教員養成期間で当時の沖縄の最高学府
「沖縄師範学校男子部」は官立の教員養成期間で、大学や専門学校のない当時の沖縄では唯一の最高学府でもありました。
そのため県内・離島各地から教師を目指すために優秀な人が集まりました。
当時の師範教育では国家主義的教育政策に即応する教員養成が目指されました。
例えば、兵式体操が導入され、さらに「沖縄県立師範学校」(沖縄師範学校男子部の前身)では他県に先駆けて御真影が導入されるなど皇民化教育、軍国教育の重要な役割を担いました。
天皇や皇后の公式の肖像写真や肖像画を敬っていう言葉。御真影は学校の奉安殿(ほうあんでん)と言われた建物に安置。戦前に広く学校に飾られた。児童は奉安殿の前を通る際に最敬礼をすることが求められた。
なお、学校は首里にあり、首里城のすぐ近くに(龍潭池のほとり)所在していました。今の沖縄県立芸術大学の場所にあり、今でも「旧沖縄師範学校正門門柱」として当時の門柱が残っています。
戦時色が強くなり、「師範鉄血勤皇隊」として動員
1944年沖縄守備軍第32軍が創設し沖縄にやってくると、校舎は接収され、その年の4月からは陣地構築などで授業がほとんど行われなくなりました。
同年12月からはすぐ近くの首里城地下に第32軍司令部壕を突貫工事で掘り続けました。
✔️あわせて読みたい
さらに第32軍司令部壕の工事と並行して自前の壕「留魂壕(りゅうこんごう)」が首里城の正殿の裏手に造成。
アメリカ軍上陸前夜、艦砲射撃激しくなると、ここを退避壕として、職員や学生の生活の場となっていきます。
今でも「留魂壕」の一部が首里城公園内に残っており数年前、一般に公開されるようになりました。
アメリカ軍が沖縄本島に開始をする前日1945年3月31日、「師範学校男子部」の全職員・学生が「師範鉄血勤皇隊」として動員され、第32軍の司令部の指揮下に入りました。
その数386名。教師になる予定だった10代の学生が戦場に駆り出されていくのです。
それぞれ「師範隊本部」「千早隊」「斬込隊」「野戦築城隊」などに分けられました。
ちなみに「沖縄師範学校女子部は」は「ひめゆり学徒隊」として動員されました。
沖縄戦での「師範鉄血勤皇隊」
「師範鉄血勤皇隊」としての任務は隊によって異なりますが、あくまでも前線ではなく、後方支援(斬込隊も)で食料の運搬や、負傷者の搬送・道路の補修などに従事しました。
しかし、後方支援の任務とは言え、任務中に激しい砲弾にあい犠牲者が増大していきます。
さらに戦況が悪化し首里にアメリカ軍が迫ってくると、一部の部隊が前戦に投入され、全滅する隊も出ます。
戦況が悪化した1945年5月後半。第32軍が首里から摩文仁に撤退(南部撤退)するのにあわせて「師範鉄血勤皇隊」も摩文仁に撤退します。
南部撤退後(ほとんどの部隊は摩文仁に撤退)も「師範隊本部」「千早隊」などの各部隊ごとに行動。しかし、摩文仁に進軍してきたアメリカ軍は火炎放射や迫撃砲で摩文仁の丘や森を焼き払います。
それでも第32軍司令部との間の伝令や、命懸けの食料調達、水汲みなどアメリカ軍の攻撃の合間を縫って行動。
摩文仁も既にアメリカ軍に囲まれ、もはや日本軍の抵抗も風前の灯となった6月18日。第32軍司令部から学徒隊の解散命令がだされます。
解散命令とは言いながらも、「師範鉄血勤皇隊は的中を突破して本島北部の国頭へ脱出して再起を図れ」というものでした。
6月23日、「師範鉄血勤皇隊」が活動していた近くの摩文仁の第32軍司令部で司令官「牛島満」中将が自決。
日本軍の組織的な抵抗は終わりましたが、摩文仁一帯はアメリカ軍の一方的殺戮場面となり、激しい攻撃を受けます。
彼らは大人の兵隊同様、捕虜になることも許されず、最後まで抵抗しろとの軍命令により、日本軍の組織的な戦闘終了後も多くの命が失われます。
日本軍の生き残りともに、敵の真っ只中に斬り込むもの。爆雷を背負って駆け去っていったもの。怪我のため自決したもの。10代の学生は四面楚歌の中、地獄の戦場に駆り出され、多くの命が失われました。
犠牲者数は226名に及びました。
- 1944年3月師範学校の校舎が軍に接収される
- 12月 首里城深くの第32軍司令部壕の構築に駆り出される
- 1945年3月23日 この頃から艦砲射撃が激しくなり、首里城正殿の裏に構築した「留魂壕」で生活を始める
- 3月31日 第32軍司令部から動員命令が出され、「師範鉄血勤皇隊」として386名が動員される
- 5月17日 特別編編成隊が組織され、弁が岳の戦いに参加し、全滅。
- 5月25日 各部隊、南部撤退開始
- 6月19日 解散命令がだされる(これ以降も多くの死傷者がでる)
- 6月23日 第32軍司令部で司令官「牛島満」中将が自決。摩文仁周辺ではアメリカ軍の一方的殺戮場面となり多くの学徒が死亡
戦死した男子学徒隊を祀る「沖縄師範健児之塔」

糸満市摩文仁にある「平和祈念公園」の東側の端の方、「牛島満」中将が自決した摩文仁の丘の頂上から下りたところに亡くなった師範学校生を祀った「沖縄師範健児之塔」があります。
「沖縄師範健児之塔」近くには近年綺麗に整備された駐車場があり、とても便利です。
那覇から国道で来ると案内板があるので、すぐにわかります。
「沖縄師範健児之塔」は1950年6月に師範学校の生き残りの方々が作りました。
周辺には学徒隊関連の慰霊碑が目立ちますが、その他2つ慰霊碑を紹介します。
「沖縄師範健児之塔」から向かって右手に「平和の像」があります。

元大田昌秀知事が戦後、「沖縄健児隊」を出版し、書籍は映画化され、その上映権で得た資金で「平和の像」を制作したのです。
もう一つは「ひめゆりの塔」や「魂魄之塔」とを建立した「金城和信」真和志村長が1946年に制作した「健児の塔」です。
✔️あわせて読みたい
「健児の塔」は師範学校だけでなく、全学徒隊を祀っています。

人生の蕾のまま戦場に散った学徒兵。生きていれば、教壇に立っていたであろう師範学校の生徒たち。
生徒の中には、「師範学校に入学したからには、一度は生徒を教えてみたかった。」と本音を語った生徒もいました。
師範学校に入学したからには、一度は生徒を教えてみたかった。
戦争は非情なものだ。どんなに勉強したくてもできない。したいことが、まだまだたくさんあったのに。戦争のない時代に生まれたかったということをのちのちの人に伝えてほしい
宮良ルリ著「私のひめゆり戦記」より一部抜粋 沖縄師範学校男子部本科2年宮良英加さんの言葉
戦争は若者の夢までも奪う。
もう二度と学生が戦争で命を失ってほしくない!そう感じさせる「沖縄師範健児之塔」や「健児の塔」です。
【沖縄師範健児之塔】
- 住所
- 沖縄県糸満市摩文仁
- 駐車場
- あり
※駐車場から徒歩5分