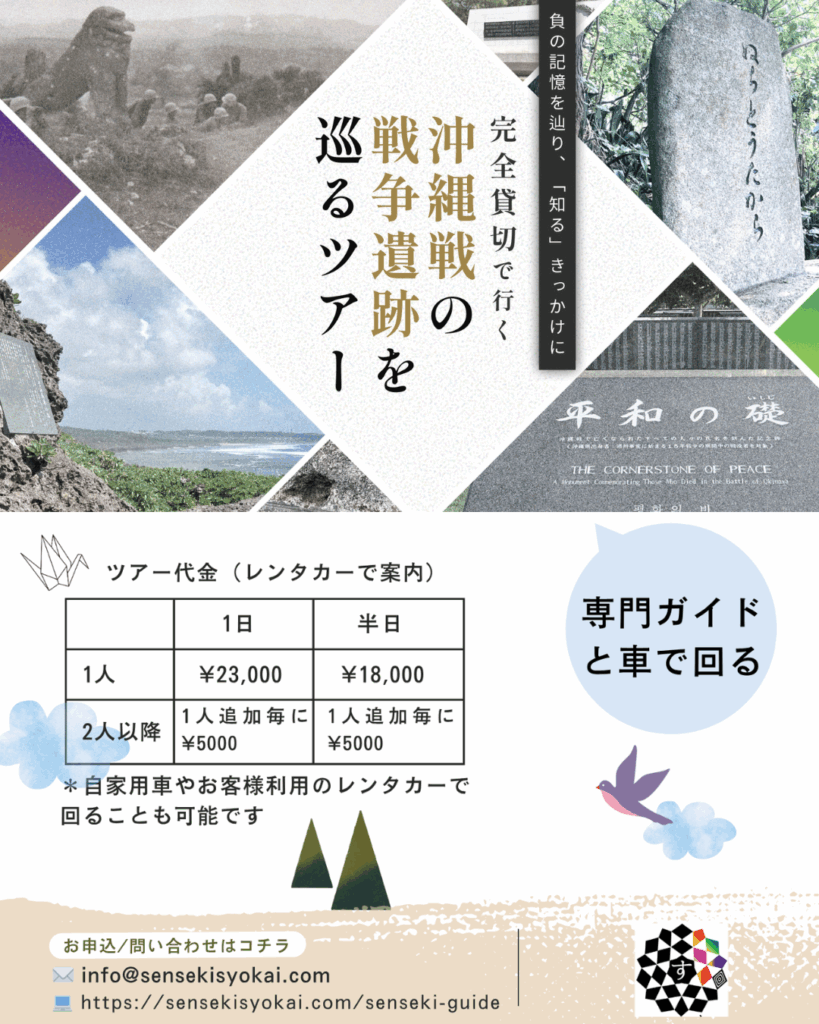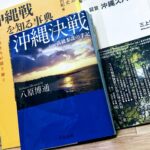糸満市南部にはさとうきび畑に囲まれたのどかな集落が各地にあります。
宇江城集落もその一つ。
各家にはシーサーが並び、石の塀に囲まれた伝統的な家や拝所などが点在し、いかにも沖縄らしい風景が見られます。
そんな小さな集落に「クラガー」と呼ばれる自然壕があります。
「クラガー」は沖縄戦時には第24師団終焉の地となりました。
師団の規模は約1万人。
1万人の組織の最後がこの自然壕(ガマ)というのはあまり想像できませんが、沖縄戦では最後に自然壕で終焉を迎えた部隊が多くありました。
第24師団は沖縄戦はどのように戦ったのか、そして「クラガー」や第24師団の慰霊碑「山雨の塔」について解説します。
第24師団の沖縄戦
第24師団は元々、中国東北部に駐留していた部隊ですが、1944年7月に師団の主力が沖縄に転用されました。
第24師団の隷下(れいか)にあった歩兵第89連隊の連隊本部が旭川にありましたので、北海道出身者の方が多かったのが特徴です。
「北海道の話を良く聞いた」
「雪の話を聞いた」などの住民の証言が残っています。
✔️あわせて読みたい
第24師団は1945年4月1日アメリカ軍本島上陸時、本島南部の島尻地区に配備され、港川(現在の八重瀬町)からのアメリカ軍上陸に備えました。
しかし、それはアメリカの陽動作戦(いわゆる囮作戦)で、1945年4月後半には戦闘が激化した首里戦線に投入されます。
5月4日の日本軍総攻撃では、攻撃の主力になりますが、(日本軍全体の戦果も含めて)唯一の戦果は隷下部隊第32連隊の棚原高地の奪取。
多くの兵力を失うことになった総攻撃は失敗。その後、再び持久作戦に転じます。
司令部にあった首里周辺でアメリカ軍の侵攻を遅らすため戦いますが、ついに首里の日本軍司令部(第32軍)がアメリカ軍に包囲され、日本軍は沖縄本島南部の摩文仁に撤退します。
✔️あわせて読みたい
第24師団終焉の地クラガー
日本軍の南部撤退にあわせて、第24師団の司令部も糸満市の宇江城(日本軍の司令部のある摩文仁から2キロ)の自然壕にうつってきます。
司令部とはいっても、もともと宇江城の住民が水汲み場として利用していた自然の洞窟。
宇江城一帯は日本軍最後の抵抗拠点の一つとなり、6月に入るとここも激戦となります。
1945年6月23日、日本軍司令官牛島司令官が摩文仁で自決し、日本軍の組織的な戦闘は終了しますが、その後も宇江城一帯では抵抗が続きます。
6月28日、壕入り口を米軍が爆破。
隷下部隊の連隊旗を奉焼。
30日、退路を絶たれた雨宮巽(たつみ)師団長並びに幕僚がこの壕で自決。

画像引用:防衛研究所
ただし、資料によって自決した日が異なる記述が見受けられる。6月24日に自決との資料もあり、いずれにせよ、死亡日時がはっきりしないということは、非常に混乱した状態であったと考えられる。
雨宮巽(たつみ)師団長の最期の様子が防衛研究所のWebサイトに掲載されていましたので紹介します。
極限状態の壕内で雨宮は、「誰か劇作家がいて、この最期を劇にすればきっと素晴らしいものになるだろうなあ」と独り言をいい、自決したといわれます。
「クラガー」の上に建つ「山雨の塔」

冒頭紹介したのどかな宇江城集落内に「クラガー」が現在でも残っています。
戦後、クラガーの上に生存者の手で「雨宮中将戦没の跡」という木柱が建てられた。昭和37年10月、沖縄県遺族連合会が沖縄協会の委託を受け現在の塔に改修し、「山雨の塔」となりました。
第24師団の通称「山部隊」と「雨宮師団長」から名付けられた。

クラガー自体は柵に囲まれていますが、施錠はされていなく中に入ることができます。しかし夏場は画像のように草が生い茂っていたり、壕内に入れたとしてもすぐに水が溜まっているので、中に入るのはおすすめしません。
以前、私が訪れた際は、第24師団の北海道の遺族の方が周辺の遺骨収集のため、クラガーを綺麗にされていました。

ご遺族の方に伺うと、毎年来られているとのことです。
師団の司令部があったと想像できないのどかな風景が広がる宇江城地区。
しかし、遺骨収集のご遺族と出会い、ここが激戦地でまだまだ沖縄戦は終わっていないということを再認識しました。
【クラガー】・【山雨の塔】
- 住所
- 沖縄県糸満市宇江城110-3
- 駐車場
- なし