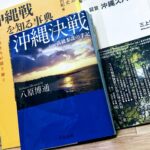「チビチリガマ」から直線距離1キロの場所に「シムクガマ」があります。「シムクガマ」も「チビチリガマ」同様にアメリカ軍に包囲されました。
しかし、「チビチリガマ」とは違い、「シムクガマ」に避難した住民は大勢助かりました。
同じ地区にあるガマでも何故このように違うのでしょうか?
本記事で「シムクガマ」での出来事を紹介します。
✔️合わせて読みたい
多くの避難民が助かった「シムクガマ」
シムクガマは総延長2570メートルの自然壕です。沖縄戦当時、波平の住民1千名が避難していました。
1945年4月1日読谷村の海岸から上陸したアメリカ軍は、圧倒的物量と兵力で瞬く間にシムクガマに押し寄せてきました。ガマにいた住民は恐怖のあまりパニックになります。
✔️合わせて読みたい
いよいよアメリカ軍の攻撃が始まり戦車砲がガマの入り口に炸裂、さらにアメリカ兵がガマにやってきました。そこで壕の中にいたハワイ帰りの移民2名がアメリカ兵と交渉することになりました。必死にアメリカ兵と交渉をした結果(移民の2人は英語を話すことができました。)、中に住民がいるとわかったため、攻撃を中止します。
その後、移民2名は住民をガマをでるため説得を開始しました。捕虜になることを恐れていた住民を「アメリカ兵は決して住民を殺さない」と説き、住民は投降し命が助かりました。助かった住民は1千人前後だと言われています。
現在、洞窟内にはその2名に感謝の意をこめて記念碑が建立してあります。
住民の命を助けたガマ。ガマは悲劇の場所というイメージが強いと思いますが、実際多くの方が助かった事例もたくさんあります。
シムクガマ
- 住所
- 沖縄県中頭郡読谷村波平438
- 駐車場
- なし
- 電話番号
- 098-958-2229(波平公民館)
マップアプリでは非常にわかりずらいです。訪問の際、場所がわかなければ波平公民館(読谷村波平655)に立ち寄りましょう。
またシムクガマは入豪可能(自然洞窟なので入壕はおすすめしません)ですが、ガマ内に川の水が流れ込んでおり、足場が悪く、雨天の際は水量が増水する恐れがあります。そのため、極力運動靴で懐中電灯・軍手などをご持参ください。
の