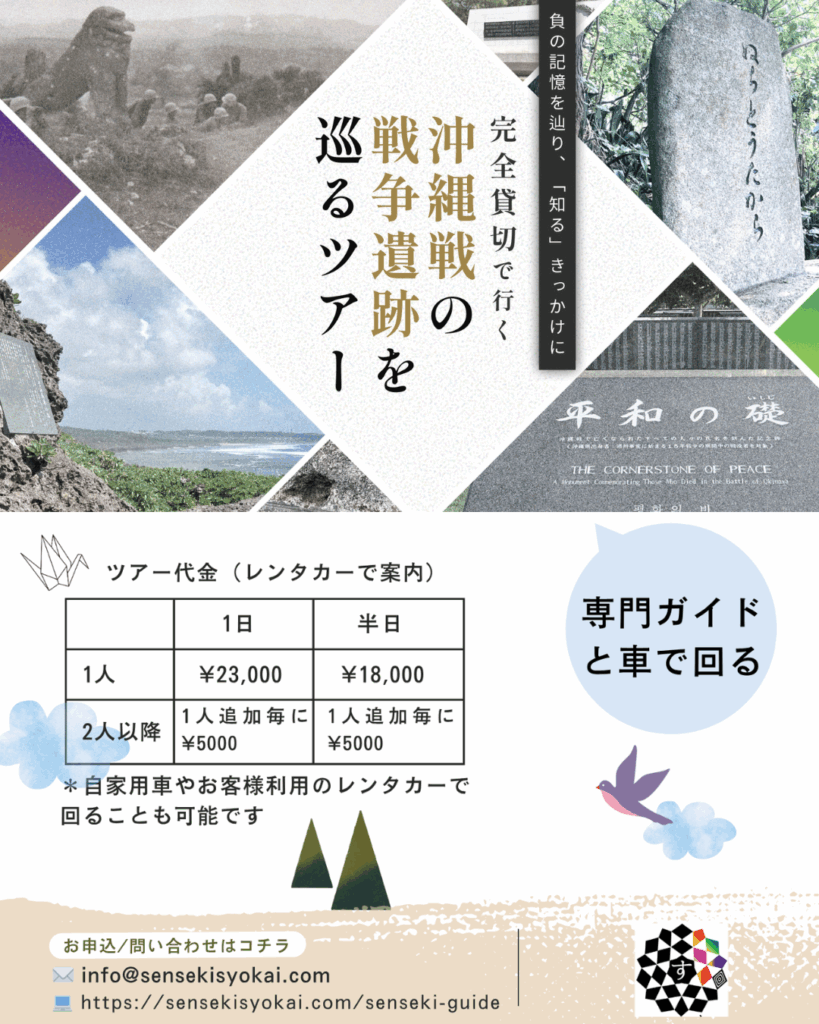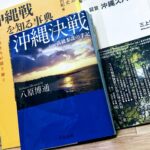沖縄戦では根こそぎ動員と言われ、地元沖縄の人たちも大勢召集され、多くの方が亡くなりました。
数多くある部隊の中に、隊長を含む全員が沖縄出身者で構成された部隊がありました。
部隊の名は「特設警備第223中隊」、通称「永岡隊」です。
地元の人々で構成された「永岡隊」とはどのような部隊だったのか?生存者の過酷な証言のもとこの記事で紹介します。
郷土部隊「永岡隊」とは
「永岡隊」は、正式には「特設警備第223中隊」と呼ばれ、隊長を含め全員が沖縄出身者で構成された、異例な部隊でした。
一般的に、沖縄出身者は学徒隊・防衛隊・軍属といった形で本土出身将校の指揮下に置かれることが多く、永岡隊は隊長も沖縄人で、すべて沖縄出身者だけの編成という点で特異でした。
隊長は安国寺の住職であり県立一中の教師でもあった「永岡敬淳」大尉が率いました。いくつかの資料によると、那覇市近郊の在郷軍人約 240 名に待命令状を出したとのことです。
待命令状とは、いつでも招集に応じられるよう待機を命じた令状で、特設と名がつけられ有事の際、軍に称する変則的な部隊のことです。
「永岡隊」は地元出身者のみで編成されたため、地域事情や地形に詳しいということで警備を担うよう命じられます。
「永岡隊」の沖縄戦
生存者の「翁長安子」さん(看護要員、兼、炊事要員で入隊。当時、県立第一高等女学校に通う15歳)の証言によると、「永岡隊」は、沖縄戦が始めると首里城近くの「識名」にいました。
翁長さんは現在も当時の話を講演会等でお話しされます。筆者も何度か講演を聞く機会があり、貴重なお話を伺うことができました。現在、90代半ばながら、当時のことを話す様子はまるで昨日のようにお話しされます。振り絞る言葉から自身の体験談を後世に紡いでいきたい、、そう強く感じさせます。
沖縄戦開始時の1945年4月ごろは、前線がまだ遠くだったこともあり、「識名」は静かだったようです。
部隊は、最初は識名におりまして、ここには 4 月 16 日か、18 日に来ました。その頃は(攻撃は)それほど激しくはありませんでした。
「翁長安子」さんの証言より
その後「永岡隊」は、首里周辺のさまざまな壕や陣地に別れて入り、戦闘を続けていきます。
5月に入ると、主戦場は首里周辺に移り、シュガーローフの戦いなど首里周辺は激戦となります。日本軍はもとより、米軍にも大きな被害が出るのです。
✔️あわせて読みたい
翁長さんの証言によると、「永岡隊」は夜になったら切り込み隊に行ったそうです。その中には県庁や学校の指導者などで、兵役の経験がある人だったとのこと。
家族を疎開させて居残り命令が出ている人が2月末に呼び集められて作られたのが永岡隊でした。その中には、私 の女学校の 1年、2年の担任の先生もおられました。
「翁長安子」さんの証言より
アメリカ軍が首里城に差し迫った5月16日ごろ、「永岡隊」は、隊長が住職をつとめ首里城のすぐ近くにある「安国寺」の壕へ移ります。
「安国寺」は日本軍第32軍司令部があった首里城から400~500メートルしか離れていない場所です。
砲弾降り注ぐ中、安国寺の壕を拠点に首里城攻防戦に巻き込まれます。
そして日本軍第32軍司令部は5月後半、首里城を放棄して、南部摩文仁に撤退することを決めます。
✔️あわせて読みたい
しかし「永岡隊」は「郷土部隊として最後まで首里を守れ」と命令が出され、アメリカ軍に包囲された中、首里に取り残されてしまいます。
32 軍が南部撤退を始めた日が 27 日です。その晩、自然の雨と弾の雨が降る中を、糸数 先生が 32 軍の命令を伝えに来ました。永岡隊は郷土部隊だから最後まで残れという命令 が出ました。子どもながらに「ひどいなあ」と思いました。32 軍が撤退した後は、首里を 守る部隊は、私が知る限り壕の中にいる 30 名くらいしかいません。
「翁長安子」さんの証言より
第32軍の司令部撤退に合わせて、少しでもアメリカ軍に損害を与える殿(しんがり)のような役割でした。
首里を占領したアメリカ軍は問答無用に「安国寺」の壕にも攻撃をします。火炎放射や黄燐弾などの馬乗り攻撃で、「永岡隊」は多くの死傷者を出します。
「29日の朝4時頃。水汲みに行って戻ってきたら、ゴーと戦車の音がしたんですよね。そしたらトンボ(米軍偵察機)も飛んできた。いつも朝6時頃しかトンボは飛ばないのにおかしいなって思ったら、戦車砲がボーンと1発飛んできた。しばらくしたらまた2発目が飛んできたんですよ。何分も経たないうちに、そしてすぐ火炎放射器」
「翁長安子」さんの証言より
第32軍から南部撤退の許可をえた、「永岡隊」は壕を脱出します。翁長さんも隊長に手を引かれ壕を脱出しますが、混乱の最中、隊とはぐれ一人で南部に移動していきます。
その後、なんとか南部の壕(轟の壕)まで辿りたついた翁長さんは、「永岡隊長」を含む生存者40名ほどと合流、ほどなくしてさらに違う壕へ移動。
6月22日「永岡隊長」は翁長さんに「生きてこんな戦があったことを語ってくれ」と言われ、壕内で自決。
翁長さんはその言葉を守り、壕を出て生き延びることができました。
「安国寺」内にある「特設警備第223中隊永岡隊慰霊之碑」

首里城内の「守礼門」や世界遺産「玉陵」にほど近く、まさに琉球王国時代の中心地と言える場所に「安国寺」はあります。
「安国寺」の正面には沖縄県立首里高等学校(戦前の沖縄県立第一中学校)があるので、わかりやすいでしょう。
✔️あわせて読みたい
「安国寺」のホームページによると歴史は古く、創建は何と1457年と琉球王国第6代「尚泰久王」まで遡る、由緒ある臨済宗のお寺です。


境内には、「永岡隊」のいた壕の後や、「永岡隊」を祀る「特設警備第223中隊永岡隊慰霊之碑」があります。
「永岡隊」のいた壕の後は既に埋められており、跡地とされる場所に石碑や記念物が設けられています。境内の奥には「特設警備第223中隊永岡隊慰霊之碑」が建立されています。
地元の沖縄の人だけで構成され、さらに日本軍が首里城撤退する際、最後まで首里を守るため殿(しんがり)のような役目でアメリカ軍の中、取り残された「特設警備第223中隊」。
過酷な任務を負わされ、そして郷里沖縄の荒廃した姿を見てどのように感じたのか…隊長が住職を務めていた安国寺で想いを馳せた筆者でした。
【特設警備第223中隊永岡隊慰霊之碑】
- 住所
- 沖縄県那覇市首里寒川町1-2※参拝後は速やかに出ましょう
- 駐車場
- あり
- ホームページ
- https://www.taiheizan-ankokuji.com/