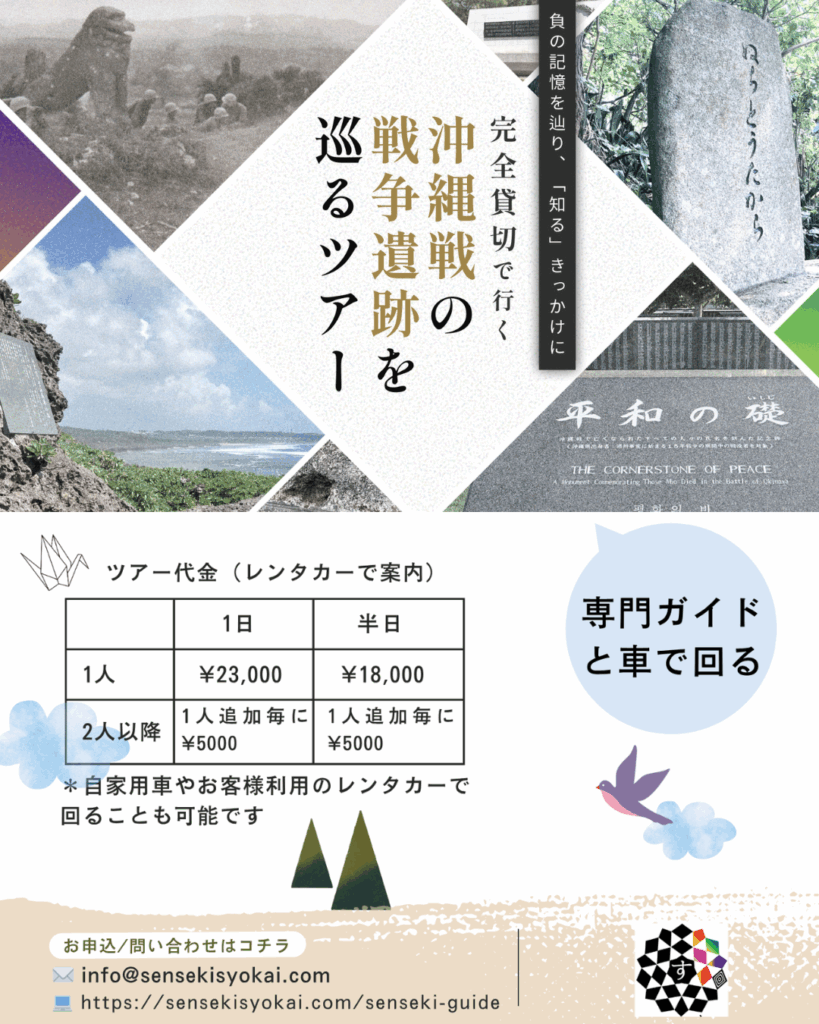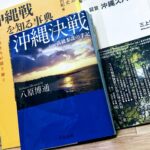シムクガマ 一般社団法人読谷村観光協会提供
「チビチリガマ」から直線距離1キロの場所に「シムクガマ」があります。「シムクガマ」も「チビチリガマ」同様にアメリカ軍に包囲されました。
しかし、「チビチリガマ」とは違い、「シムクガマ」に避難した住民は大勢助かりました。
同じ地区にあるガマでも何故このように違うのでしょうか?
本記事で「シムクガマ」での出来事を紹介します。
✔️あわせて読みたい
「シムクガマ」はなぜ多くの人が助かったのか
「シムクガマ」は総延長2570メートルの自然壕です。沖縄戦当時、読谷村波平の住民約千名が避難していました。
1945年4月1日読谷村の海岸から上陸したアメリカ軍は、圧倒的物量と兵力で瞬く間に「シムクガマ」に押し寄せてきました。ガマにいた住民は恐怖のあまりパニックになります。
✔️あわせて読みたい
いよいよアメリカ軍の攻撃が始まり戦車砲がガマの入り口に炸裂、さらにアメリカ兵がガマにやってきました。そこでガマの中にいたハワイ帰りの比嘉平治さんと比嘉平三さんの2人の方がアメリカ兵と交渉することになりました。
必死にアメリカ兵と交渉をした結果(移民の2人は英語を話すことができました。)、中に住民がいるとわかったため、攻撃を中止します。
その後、2名は住民をガマをでるため説得を開始しました。捕虜になることを恐れていた住民を「アメリカ兵は決して住民を殺さない」と説き、住民は投降し命が助かりました。助かった住民は千人前後だと言われています。
しかし「シムクガマ」の実相として全ての住民がこの2名の説得でガマでたわけではありません。家族の判断でガマを出た住民もいます。
読谷村史の戦時記録を見ると、ガマの奥にいた家族の証言で「移民2名の方が説得した話」は戦後聞いたと話されています。
シムクガマの多くの避難民の命を助けるため、二人のハワイ帰りの人が尽力されたということが知られるようになりました。しかし、彼らだけの力で壕内に潜んでいた一〇〇〇名近い人々の意見が半日のうちに「投降」へとまとまるわけもありません。壕の後方にいた私たちが見聞きしたところでは、あの時は様々な人の意見が壕内を駆け巡っていたのです。当時父のような大人の男性は壕には少なく、しかも父は軍隊の経験もありました。その父が「抵抗するな」と言ったというのは大きな影響力になったと思います。父には入口付近の動きは分かりませんでしたが、知らないうちに「投降への協力者」の一人になっていたのです。
『読谷村史戦時記録』より
いずれにせよ、「投降という判断ができる人が近くにいたこと」により、生きてガマを出ることができたのです。
住民の命を助けたガマ。ガマは悲劇の場所というイメージが強いと思いますが、実際多くの方が助かった事例もたくさんあります。
現在の「シムクガマ」
「シムクガマ」は今でも当時のまま、残っています。
「シムクガマ」までの道は比較的整備されているので、壕内に入ることもできます。
ただし、マップアプリでは非常にわかりずらいですし、ガマ内に川の水が流れ込んでおり、足場が悪く、雨天の際は水量が増水する恐れがあります。
専門のガイドと訪問してください。
また洞窟の入り口には比嘉平治さんと比嘉平三さんに感謝の意をこめて記念碑が建立してあるので、見学できます。
先に紹介した「チビチリガマ」と「シムクガマ」両ガマを訪れることで、命を分けたもの、そして沖縄戦の本質について考えることができます。

【シムクガマ】
- 住所
- 沖縄県中頭郡読谷村波平438
- 駐車場
- なし
- 電話番号
- 098-958-2229(波平公民館)
マップアプリでは非常にわかりずらいです。タクシーもしくは専門のガイドと訪問してください。
またシムクガマは入豪可能(自然洞窟なので入壕はおすすめしません)ですが、ガマ内に川の水が流れ込んでおり、足場が悪く、雨天の際は水量が増水する恐れがあります。そのため、極力運動靴で懐中電灯・軍手などをご持参ください。
の